📅 今日は何の日?
蒸し暑い夏の夜に、ひんやりと背筋をなでるような不思議な怖さ…。
そんな日本独自の“涼”を届けてくれるのが、7月26日の「幽霊の日」です🌬️🕯️
この日は、江戸時代を代表する怪談歌舞伎『東海道四谷怪談』が初めて上演された日。
お岩さんの悲しくも恐ろしい物語を通じて、日本の怪談文化が深く人々の心に刻まれました。
「幽霊の日」は、日本の伝統的な怪談や幽霊像に触れ、文化としての“怖さ”を味わう1日なのです📚🎭
👘「幽霊の日」ってどんな日?
「幽霊の日」は、1825年(文政8年)7月26日に、江戸の中村座で鶴屋南北作『東海道四谷怪談』が初演されたことにちなみ制定された記念日です。
『四谷怪談』は、夫に裏切られた女性・お岩が幽霊となって復讐を果たすという物語。
そのリアルな心理描写と恐怖演出が観客に衝撃を与え、日本の怪談文化を象徴する名作となりました。
この作品は、歌舞伎、映画、テレビ、落語など多くのジャンルに影響を与え、“幽霊”の定番的なイメージをつくり出す土台となった歴史的な作品でもあります👻🎞️
📅 なぜ7月26日?
- 1825年7月26日、江戸の中村座にて『東海道四谷怪談』が初演🎭
- 作者は、江戸後期の名作家鶴屋南北
- 江戸の市民に“本当にあった話”と思わせるほどのリアリティが話題に🗣️
そのインパクトの強さから、7月26日は怪談の象徴的な日=「幽霊の日」として記憶されるようになりました。
👻 幽霊文化の魅力を再確認!
✅ 白装束に足がない姿は、日本独特の幽霊像!
→ 丸山応挙の幽霊画や歌舞伎演出がその原型とされています🖼️
✅ 「うらめしや〜」のセリフとポーズも定番!
→ 両手を前に差し出す姿が、視覚的な“恐怖”を演出😨
✅ 幽霊は“怖さ”だけじゃない!
→ 無念・悲しみ・愛情など、感情の深さが物語に奥行きを与えています💔
✅ 怖さの中にある“文化的美”を感じられる!
→ 歌舞伎や浮世絵、怪談文学など多くの芸術とつながる存在📜
🎉「幽霊の日」の楽しみ方アイデア
📖 怪談話を読んで、日本の怖さにふれてみよう
→ 『四谷怪談』『牡丹灯籠』『耳なし芳一』など、名作を読破👀
🎥 ホラー映画やドラマで涼を感じる1日を!
→ 日本の幽霊映画は心理的な怖さが魅力🎬
⛩️ 於岩稲荷田宮神社を訪ねてみよう
→ お岩さんゆかりの東京・四谷にあるスポットで歴史を実感⛩️
📱 SNSで「#幽霊の日」をつけて怪談をシェア!
→ あなたの体験談やおすすめの作品を投稿して、怖さを分かち合おう👻
🗣️ 友人や家族と“怪談語り”をしてみる
→ 夏の夜に語る怪談は、怖さ以上に記憶に残る体験に…🌙
✅ まとめ
7月26日の「幽霊の日」は、江戸時代の怪談歌舞伎『東海道四谷怪談』の初演を記念して生まれた、日本の怪談文化を称える1日です。
お岩さんの物語をはじめ、幽霊という存在は日本人の想像力と美意識を刺激し、文学や芸術に深く影響を与えてきました。
暑さが厳しいこの季節、背筋をスッと冷やしてくれる“文化的な怖さ”を体感することで、涼を楽しむ粋な時間が過ごせるかもしれません。
今日という日をきっかけに、怪談の世界に一歩足を踏み入れてみてはいかがでしょうか?
あなたの心に残る“ひと夏の怖い話”が、そこにあるかもしれません…🕯️👁️🗨️

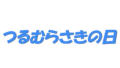
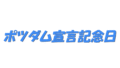
コメント