📅 今日は何の日?
7月7日の七夕、覚えていますか?🎋
実はもうひとつの“七夕”があるんです。
それが、8月7日に祝われる「月遅れ七夕(つきおくれたなばた)」✨
旧暦の七夕により近い季節感を大切にしたこの日。
特に北海道や東北、信州などの地域では、今もこの日を本来の七夕として大切にしています🌌
涼やかな夜風とともに星空を見上げる——そんな、夏の終わりの風情が漂う記念日です🎐💫
🌟 「月遅れ七夕」ってどんな日?
「月遅れ七夕」は、旧暦の7月7日を現在の暦に置き換えた行事として、毎年8月7日に行われます。
明治時代に暦が太陽暦(新暦)へ移行したことで、旧暦の七夕が真夏の気候とずれてしまいました。
そのため、かつての季節感を守るために“1か月遅れ”で祝う文化が生まれたのです🎋
北国や山間部では、8月の方が旧暦に近い自然のリズムで七夕を楽しめることから、今でも「本来の七夕」として地域に根付いています。
涼やかな夜空に天の川がきらめく季節に祝うからこそ、より風情ある時間が流れます🌠✨
📅 なぜ8月7日が「月遅れ七夕」?
1873年(明治6年)の改暦により、日本は太陽暦へと移行しました📅
旧暦7月7日は、新暦では年によって異なりますが、概ね8月上旬頃にあたります。
とはいえ、7月7日の新暦七夕では梅雨の真っ只中で天気も不安定☔
「星に願いを」と言っても、天の川どころか星が見えないこともしばしば…。
そこで、気候が安定し星空が美しく見える8月7日を「月遅れ七夕」として祝うようになりました✨
仙台七夕まつりなど、日本を代表する七夕行事もこの日程に合わせて開催されているんですよ🎉
🎋 月遅れ七夕の魅力を再確認!
✅ 旧暦に近い季節感で楽しめる七夕
→ 真夏の夜空に広がる天の川、幻想的な星空がロマンチック🌌
✅ 地域の風習や伝統が息づく行事
→ 仙台七夕、ローソクもらいなど独自の文化を体験🎭
✅ 子どもから大人まで楽しめるイベント
→ 短冊に願いを書いたり、笹飾りを作ったり家族時間も◎👨👩👧👦
✅ 夏の終わりにふさわしい涼やかな夜の風情
→ 風鈴、浴衣、灯り…五感で味わう日本の夏🎐
💡「月遅れ七夕」の楽しみ方アイデア
🎋 家庭で七夕飾りを作ろう
→ 笹に願い事を書いた短冊を飾れば、家の中でも七夕気分に🎨
👘 浴衣を着て地域のイベントに参加
→ 伝統的な装いで夏祭りや灯りの演出を満喫✨
🌌 星空観察をしてみよう
→ 織姫星(ベガ)と彦星(アルタイル)を探して、神話に思いを馳せよう🌠
📸 SNSで「#月遅れ七夕」を検索&投稿
→ 他の人の願いや飾りつけ、イベントの様子を見るのも楽しい😊
📚 織姫と彦星の伝説を読み聞かせ
→ 子どもたちと一緒に、ロマンあふれる物語に触れる夜を🎑
✅ まとめ
8月7日の「月遅れ七夕」は、旧暦に根ざした本来の七夕の姿を今に伝える貴重な行事です。
地域によって形は異なれど、どの土地でも共通しているのは「星に願いを込める心」。
夜風が少し涼しく感じられるこの季節に、浴衣をまとって星を見上げる——
そんな時間こそが、日本ならではの情緒を感じさせてくれます。
短冊に願いを綴り、遠い空の織姫と彦星に思いを託す夜。
あなたも今年は、月遅れの七夕に参加してみませんか?🌌🎋

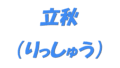

コメント