📅 今日は何の日?
介護や看護の現場で耳にする「床ずれ」。
医学的には「褥瘡(じょくそう)」と呼ばれ、長時間の圧迫によって血流が滞り、皮膚やその下の組織が損傷してしまう状態を指します⚡
そんな床ずれへの理解と予防意識を高めるために制定されたのが、10月20日の「床ずれ予防の日」🩺✨
制定したのは、褥瘡の研究と啓発に取り組む 一般社団法人日本褥瘡学会。
この日は、「床ずれは予防できるもの」という正しい知識を広め、患者さんだけでなく家族や介護者も安心できる環境づくりを呼びかけています🌸
🏢 「床ずれ予防の日」ってどんな日?
「床ずれ予防の日」は、褥瘡の正しい理解を広めることを目的に制定されました。
寝たきりや車椅子生活を送る方にとって、床ずれは避けられないものだと思われがち。
しかし、体位変換や適切な寝具、栄養管理などを行うことで、十分に予防できる疾患です。
一般社団法人日本褥瘡学会は、研究成果を広く発信しながら、医療・介護現場での知識向上や啓発活動を続けています。
この記念日を通して「正しい知識が大切な人を守る」というメッセージを届けています✨
📅 なぜ10月20日?
10月20日が選ばれた理由は、わかりやすい語呂合わせ📅
- 10=床(とこ)
- 20=ずれ
組み合わせると「床ずれ」と読めることから、この日が記念日に定められました。
覚えやすい語呂で、多くの人に意識してもらう狙いが込められています💡
🛏️ 床ずれとは?
✅ 医学的には褥瘡(じょくそう)
→ 長時間の圧迫によって血流が悪くなり、皮膚や組織が壊れてしまう。
✅ 高齢者や寝たきりの方に多い
→ 自分で体を動かせないため、圧迫が続きやすい⚡
✅ 放置すると重症化の恐れ
→ 感染症や疼痛を引き起こし、生活の質(QOL)低下につながる😨
✅ 予防できる疾患
→ 体位変換・体圧分散寝具・スキンケア・栄養管理が有効💡
床ずれは「避けられないもの」ではなく、「正しいケアで防げるもの」。この認識を広めることが大切です✨
🎉 「床ずれ予防の日」の過ごし方アイデア
📖 床ずれについて学ぶ
→ 家族や介護する方と一緒に予防法を知る。
🛏️ 寝具を見直す
→ 体圧を分散できるマットレスやクッションを取り入れる。
🤲 定期的な体位変換
→ 2時間おきに姿勢を変えるなど、血流を保つ工夫を。
🥗 栄養と水分補給
→ タンパク質・ビタミンをしっかり摂り、健康な皮膚を維持。
📸 SNSで啓発を発信
→ 「#床ずれ予防の日」をつけて知識をシェアし、広める📣
✅ まとめ
「床ずれ予防の日」は、患者さんや介護する人が“安心して生活できる環境”を考えるための記念日です。
10月20日という日付には「床(とこ)」「ずれ」の語呂合わせが込められ、覚えやすく、日常に取り入れやすいものになっています。
床ずれは“避けられない病気”ではありません。
体位変換や寝具の工夫、栄養管理といった日常のケアによって防ぐことができます。
この日をきっかけに、ご家族や身近な人と一緒に「床ずれ予防」について考えてみませんか?
10月20日は「床ずれ予防の日」🛏️✨
小さな気づきと行動が、大切な人の健康と笑顔を守ります😊
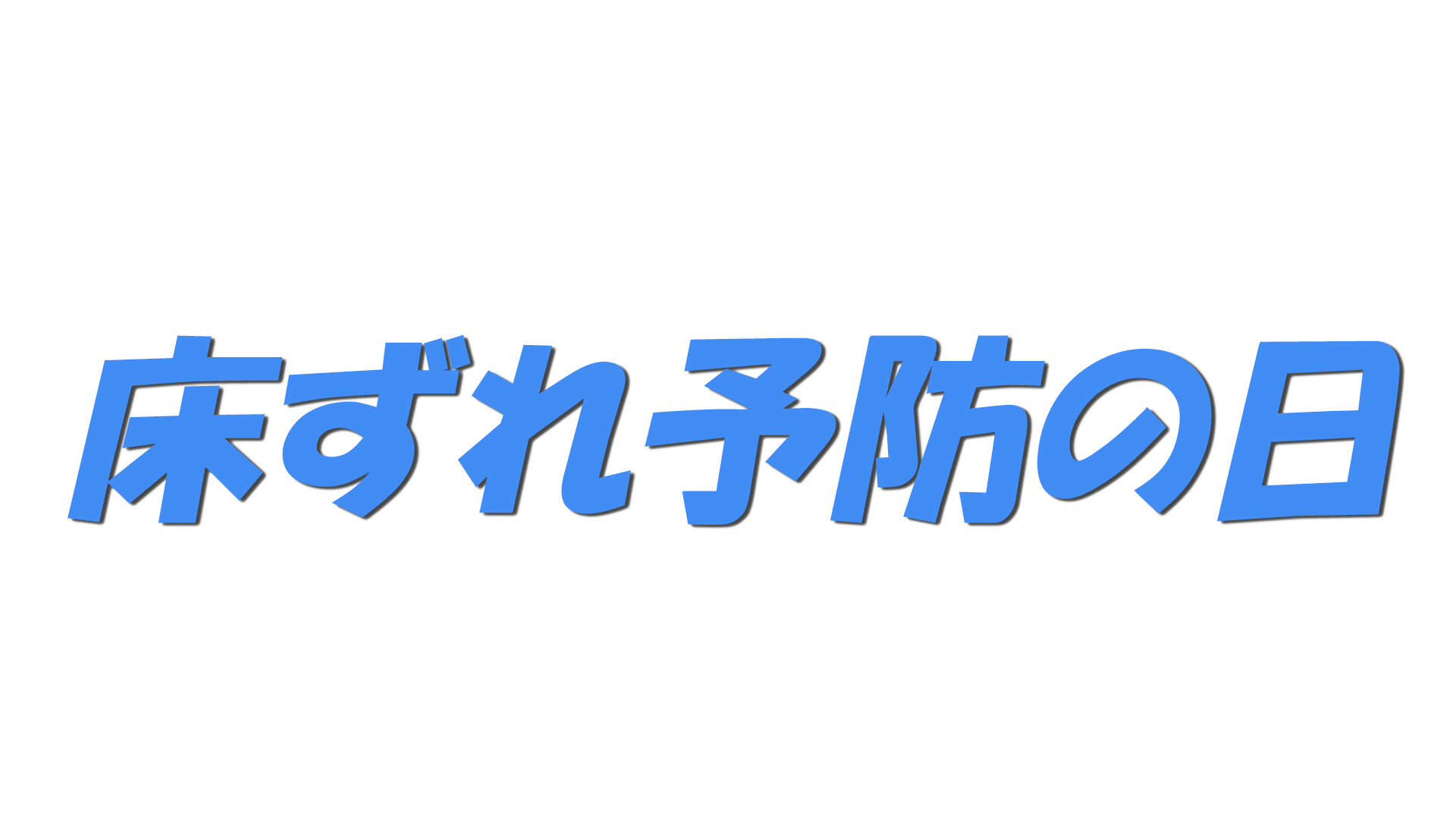
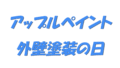

コメント