📅 今日は何の日?
1月7日は「千円札発行の日」💴✨
1950年(昭和25年)のこの日、新円切替後初の千円紙幣が正式に発行されました📅
初代千円札には、表に聖徳太子、裏に法隆寺夢殿が描かれ、戦後日本の復興を象徴する紙幣として多くの人に希望を与えました🏯✨
当時は千円が今よりもずっと高額で、まさに“豊かさの象徴”。
新しい時代への一歩を刻んだ記念すべき日です💪🇯🇵
💱 「千円札発行の日」ってどんな日?
この日は、日本の通貨制度が再出発した日として記念されています💴
第二次世界大戦後、日本はインフレーションと通貨混乱に直面。
その信頼を取り戻すために実施されたのが「新円切替」制度でした📜
そして1950年1月7日、正式な新円として登場したのが、B号千円札(聖徳太子札)です✨
平和と文化の象徴である聖徳太子の肖像は、“日本が再び調和と繁栄を取り戻すように”という願いを込めたデザインでした🙏
以降、千円札は時代ごとに姿を変えながらも、日本人の暮らしにもっとも身近な紙幣として親しまれ続けています💴
📅 なぜ1月7日?
この日が選ばれたのは、実際に新しい千円紙幣が発行された日だからです📅
1950年1月7日、戦後の混乱を乗り越えた日本経済の新しい一歩として、“B号聖徳太子千円札”が世に出ました💴✨
この出来事は、日本が「物とお金の信頼を取り戻す」重要な転換点。
千円札はやがて国民の生活に根付き、今では日本経済の象徴とも言える存在です💫
💴 千円札の魅力を再確認!
✅ 時代とともに進化するデザイン
→ 各時代を代表する偉人や文化が描かれ、“日本の顔”として愛される🎨
✅ もっとも身近な紙幣
→ 自販機・お釣り・旅先など、生活のあらゆる場面で活躍💵
✅ 世界屈指の偽造防止技術
→ 透かし・ホログラム・すかし彫刻など、職人技と科学の融合🔬
✅ 文化と経済をつなぐ日本の象徴
→ 紙幣一枚に、歴史・芸術・技術の物語が込められている🇯🇵✨
💡 歴代千円札のデザイン変遷
| 発行年 | 表の肖像 | 裏の図柄 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1950年(B号) | 聖徳太子 | 法隆寺夢殿 | 戦後復興の象徴。新円切替後初の正式千円札。 |
| 1963年(C号) | 伊藤博文 | 日本銀行本店 | 日本初の内閣総理大臣。近代国家の礎を表す。 |
| 1984年(D号) | 夏目漱石 | 鶴と富士山 | 文学と自然の調和を描いたデザイン。 |
| 2004年(E号) | 野口英世 | 富士山と桜 | 医学と自然の力を融合。世界的な科学者を象徴。 |
| 2024年(F号) | 北里柴三郎 | 葛飾北斎「神奈川沖浪裏」 | 科学と芸術の融合。最新偽造防止技術搭載。 |
💡豆知識:紙幣の「A号」「B号」ってなに?
実は日本銀行券には、発行シリーズ(号券)という区分があります。
これは紙幣のデザインや偽造防止技術が刷新されるたびに変わるもので、
「A号 → B号 → C号 → D号 → E号 → F号」とアルファベットで区分されています📖
| 号(シリーズ) | 発行時期 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| A号券(1946年) | 戦後直後に発行。肖像なしの簡易紙幣。 | 経済安定のため緊急的に発行。 |
| B号券(1950年) | 聖徳太子の千円札登場。 | 新円切替後の正式な新紙幣。 |
| C号券(1963年) | 伊藤博文ら近代偉人が登場。 | 高度経済成長期を象徴。 |
| D号券(1984年) | 夏目漱石など文化人。 | カラー印刷と偽造防止強化。 |
| E号券(2004年) | 野口英世・樋口一葉・福沢諭吉。 | ホログラム導入。 |
| F号券(2024年) | 北里柴三郎ほか。 | 最新のセキュリティ技術搭載。 |
つまり「1950年(B号)」という表記は、戦後の暫定紙幣(A号)の次に登場した正式な新シリーズを意味しているんです💴✨
🎉 「千円札発行の日」の楽しみ方アイデア
💴 歴代デザインを比べてみよう
→ 各時代の肖像や背景を調べると、日本史の学びにも📚
🏛️ 貨幣博物館を訪れてみる
→ 実物の旧紙幣を見学できる貴重な体験💫
🪙 お札コレクションを始めてみる
→ 小さな趣味が日本文化を知るきっかけに✨
📱 SNSで「#千円札発行の日」を投稿
→ “お金にまつわる豆知識”をシェアして盛り上がろう💬
✅ まとめ
1月7日の「千円札発行の日」は、戦後日本の再出発を記念する日💴✨
1950年、聖徳太子が描かれたB号千円札が誕生し、その後も千円札は時代とともに進化しながら、日本の暮らしを支えてきました🌸
今日、お財布の中にある一枚にも、歴史・文化・技術の物語が込められています。
ぜひこの機会に、お札のデザインに宿る“日本の歩み”を感じてみてください😊💫

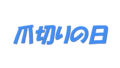

コメント