📅 今日は何の日?
12月11日は「百円玉記念日」💡
1957年(昭和32年)のこの日、日本で初めて百円硬貨が発行されました。
それまで百円といえば紙幣で、明治時代から長く流通していたのは板垣退助の肖像が描かれた百円札。
しかしこの日から、私たちの生活に馴染み深い“硬貨”として登場することになったのです💴✨
当時発行された百円玉は銀貨で、表面には鳳凰、裏面には旭日と桜花がデザインされました。
キラリと輝く銀の百円玉は、人々に新しい時代の象徴として受け入れられたのです🌸🦚
💴 「百円玉記念日」ってどんな日?
「百円玉記念日」は、日本における貨幣制度の大きな転換点を記念した日です。
それまでの「紙幣」から「硬貨」へ。
特に百円は日常生活で使用頻度の高い単位であり、その切り替えは社会に大きなインパクトを与えました。
1957年に登場した初代百円玉は銀貨で高級感があり、その後デザインや素材が変わりながらも、半世紀以上にわたり人々の暮らしを支え続けています。
まさに「百円玉記念日」は、身近なお金の歴史を振り返り、改めてその価値や役割を考えるための記念日なのです📚✨
📅 なぜ12月11日?
- 1957年12月11日に、日本で初めて百円硬貨が発行されたから!
- 百円紙幣から硬貨へ移行する大きな節目だった📅
- 以降、百円は生活に欠かせない“硬貨”として定着しました💴✨
🌸 百円硬貨の移り変わり
✅ 1957年(昭和32年)~:銀貨(鳳凰・旭日と桜花のデザイン)
→ 初代の百円玉。銀の輝きが特徴的✨
✅ 1959年(昭和34年)~:銀貨のまま「稲穂」デザインに変更
→ 豊かさと繁栄を象徴する稲穂が図柄に🌾
✅ 1967年(昭和42年)~:白銅製に変更、桜の花三輪のデザインに
→ 銀の価格高騰により素材を変更。現在もこの桜デザインが続いています🌸
素材やデザインの変化は、その時代の経済状況や社会背景を映し出す“歴史の証人”ともいえるのです。
💡 百円玉の魅力を再確認!
✅ 身近で一番使いやすい!
→ 自動販売機やコンビニなど、日常のあらゆる場面で大活躍🍹🛍
✅ デザインの変遷から歴史を学べる!
→ 鳳凰、稲穂、桜…日本文化を象徴するモチーフが描かれています📖
✅ コレクション価値がある!
→ 古い銀貨の百円玉は希少性が高く、収集家にも人気💎
✅ 子どもと学べる教材に!
→ お金の歴史や価値を考えるきっかけになり、金融教育にも役立ちます👨👩👧👦
💡「百円玉記念日」の楽しみ方アイデア
👀 財布の中の百円玉を観察してみる
→ 発行年やデザインを調べると意外な発見があるかも!
🔍 どの年号の百円玉があるかコレクションしてみる
→ 古いものを探す楽しみも。
👨👩👧👦 家族で「お金の歴史」を話題にする
→ 昔の紙幣の話や、素材の変化について語り合うのも学びに。
💎 銀貨時代の百円玉を探してみる
→ フリーマーケットや専門店でコイン収集に挑戦!
📱 SNSで「#百円玉記念日」を付けてシェア
→ ちょっとした豆知識を投稿すれば話題になるかも✨
✅ まとめ
12月11日の「百円玉記念日」は、1957年に日本で初めて百円硬貨が発行されたことを記念した日です。
銀貨の百円玉から始まり、稲穂、そして現在の桜のデザインへと姿を変えながら、半世紀以上にわたり私たちの生活に寄り添ってきました。
普段は当たり前のように使っている百円玉。
しかしその裏には、経済の変動や文化の象徴、そして人々の暮らしを支えてきた歴史があります。
今日は、ちょっと特別な気持ちで百円玉を眺めてみませんか?
きっと、あなたの手の中にある一枚が、日本の歩みを物語っているはずです💴✨


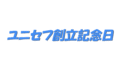
コメント